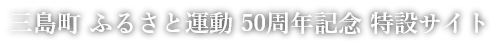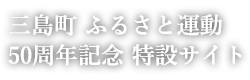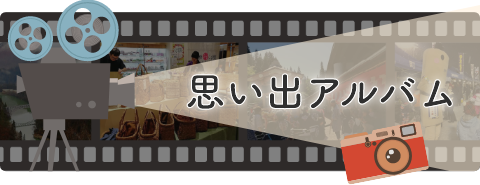本文
ふるさと運動とは
大資本の力で都市と農村を結ぶリゾート開発、三島町でも昭和40年代に大企業に土地を売って開発をしてもらおうという動きがありました。しかし、そうではなく、地元住民と都会に住む個々人の力を併せて地域づくりと観光振興を進めていこうと考え、当時の町長や役場職員が町民とともに練り上げ生まれたのが「ふるさと運動」です。
昭和48年(1973)にその構想を発表、全国紙である日本経済新聞にも取り上げられ、開始前であったにもかかわらず全国からの反響がありました。
昭和49年(1974)1月1日より正式に開始した「ふるさと運動」、その肝となるのが「特別町民制度」です。田舎に故郷を持たない都会の人々が年額1万円で特別町民になり、町では「ふるさとの家」に泊まり、田舎暮らしを体験してもらったり、地元で開発した自然公園で遊んでもらったりし、時にはその技術や知識、コネクションを活かしてもらうことで、今でいう地域づくりや地域おこしに協力いただくというものです。
当時の都会の人々が求めていた運動であり制度であったこと、また東洋信託銀行がこの運動に共感し、町と提携して「ふるさと信託」といった商品が売り出されたこともあり、特別町民は849世帯・3500名という、当時の町の人口3,837人に近い数でのスタートとなりました。
スタート時をピークに特別町民は減少傾向にありますが現在も「ふるさと運動」そして「特別町民制度」は継続中であり、令和6年(2024)にはついに50周年を迎えました。
民泊「ふるさとの家」
昭和49年にはじまったふるさと運動の目玉ともいえるものが「ふるさとの家」でした。特別町民(都会の人々)をまるで親類付き合いをしているかのように受け入れ泊まらせる家のことです。全国的にみても先駆けとなった取り組みでした。
「ふるさとの家」に登録した家は、お客様を寝泊まりさせるために改築するわけでもなく、食事も普段と同じようなものを出し、同じように寝起きします……三島町をふるさとと思ってくれる特別町民をお客様として扱わず、まるで親類の家に泊まりに来たような日々を過ごしてもらうというのが基本理念です。だからこそ「ふるさとの家」では特別町民から決まった料金ではなく、感謝の意を込めたお礼としてのお金をいただきました。
両者はだんだんと深い関係となり、中には結婚式に呼んだり呼ばれたりといった本当の親類付き合いではないかという結びつきも生まれたりしました。
ふるさと運動は今もなお続いていますが民泊「ふるさとの家」制度は、受け入れる農家の人たちと特別町民の高齢化などを理由に、現在は行っていませんがふるさとの家と特別町民の方々との交流は今も続いています。
手づくりの観光地「美坂高原」「大林ふるさとの山」
美坂高原
全国各地で企業による観光開発が行われていた昭和40年代、三島町でも土地を東京の企業に売って開発してもらおうという動きがありました。そういったなか、大企業の力を借りずに地元の力で、自分たちで自然と伝統を守りながらの開発をしたい、そういった想いが町民の賛同を得て、「ふるさと運動」の目玉の一つとして実現したのが「美坂高原」です。
「美坂高原」は大石田地区の一ノ原というかつてのカヤ場(屋根葺き等に利用するカヤの採集地)にあり、昭和40年代に牛の放牧場として利用するべく拓いた高原を、あらためて開発したものです。一ノ原からほど近い三坂山の「三」を「美」として「美坂高原」と名付け、昭和49年(1974)7月26日「美坂高原ふるさと公園」としてオープンしました。
整えられた自然環境の中で遊べるだけでなく、サイクリングや釣り、乗馬、バーベキューなどもできる自然を存分に活かした公園で、開設当初は町民・特別町民を送迎する美坂高原専用バス「ふるさと号」も運行されていました。町民や特別町民の憩いの場というだけでなく各種イベントにも大いに利用され、また会津盆地の小中学生の行楽地・遠足地として利用されるなど大変な賑わいでした。
近年は人里から離れ人工的な光の影響がほぼない中で星空の観察ができる場所として注目されており、関連イベントも毎年行われています。
大林ふるさとの山
「大林ふるさとの山」は、ふるさと運動の取り組みの一つとして、また森林総合利用促進を目指したものとして昭和49年(1974)から造成がはじまりました。同年5月には桜の山にしたいと、しだれ桜・ひがん桜・大山桜など千本の苗木が西方地区、各建設業者、観光協会、役場など約130名の人達により3ヘクタールに植えられ、現在では春に地面に咲き誇るカタクリとともに「カタクリさくらまつり」の会場として、大勢の人が訪れるようになっています。
完成後は森林公園として利用されるほか、さまざまな催しも行われました。昭和58年(1983)には都市と農村を結ぶ「ふるさと音楽祭」の会場にもなり、ふるさと運動ユネスコ協会(東京本部・三島支部)主催のもと盛大に行われ、今も残る三島町の愛唱歌、地元町民の作詞と特別町民の協力により生まれた「三島音頭」が発表されたりもしました。
なお「大林ふるさとの山」という愛称は、昭和52年(1977)に地元中学生等の応募の中から名付けられたもので、以前は「大林森林公園」と呼ばれていました。
内発的な地域づくり「三島フォーラム」
「三島フォーラム」……この名称だけでは何であったのか、想像ができないかもしれません。この「三島フォーラム」は行政と町民、そして特別町民の勉強会として、昭和57年(1982)にはじまったものです。町づくりは行政だけが先行しても成功はしない、町民が「地域をつくる」という意識があってこそとの考えから、青年会、婦人会、老人会ほか各種団体が参加し毎年行っていました。
「三島フォーラム」は故・安達生恒氏(島根大学名誉教授)を学長とし、宮崎清氏(現千葉大学名誉教授、現三島町名誉町民)を副学長として、毎回特別講師を招いていました。その第一回は埼玉県所沢市で消費者運動をしている白根節子氏、白根氏は有機農業について切々と語られました。化学肥料や農薬を用いず、土づくりを大事にし安全な食べ物をつくる、有機農業のコンセプトは三島町の有志に受け入れられ、同年三島町では「有機農業友の会」が発足、会津若松市で産物の直売会や町内で朝市を行うなど盛り上がりをみせ、このことが当時の三島町の5つの運動の一つ「有機農業運動」に結びつきました。
「三島フォーラム」は色々な人を招いての勉強会でしたが「豊かな暮らしを考える」というテーマは一貫していました。そして、このフォーラムからは、「有機農業運動」だけでなく、参加した各種団体が主催するさまざまなイベント開催のきっかけにもなりました。